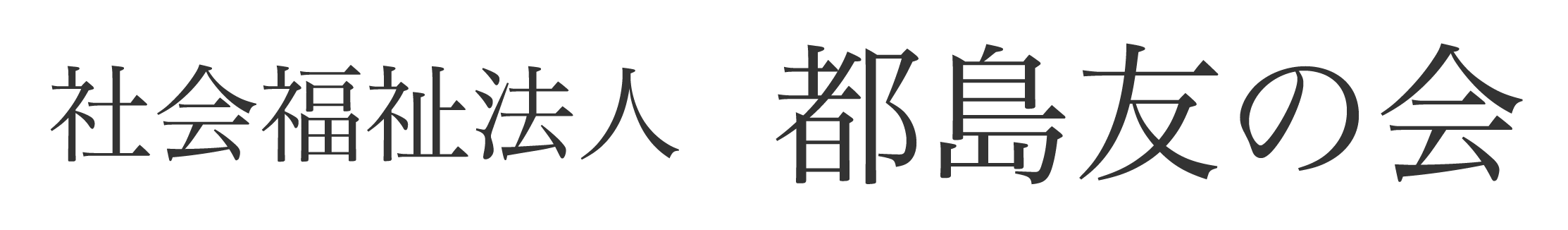暑さ、寒さも彼岸まで。
奈良に春を呼ぶ東大寺二月堂のお水取りが3月1日~14日まで、新しい年がいい年である事を祈り行事があります。天災や病や反乱など国家の災いを取り除き、人々の幸福を願う行事とされています。
当法人も令和6年3月1日で、93回目の創立記念を迎えました。昭和6年青空保育園から都島幼稚園と始まった歴史の中で、日本は満州事変から日中戦争へ、昭和20年8月終戦まで戦禍の中でした。
太平洋戦争での日本の死者は(1977年厚生省のあげた)軍人関係230万人、外地一般邦人30万人、内地戦災死者約50万人、合わせて310万人と報告されていました。尊い命が失われていきました。そこでいつも犠牲になるのが一般生活者、特に子ども達や高齢者の弱き人々です。現在においても戦禍に苦しむ世界の子ども達がいます。 昭和45年12月、比嘉正子(当時66歳)の著書、『女の闘いー死者よりも生者への愛を求めてー』のあとがきにこのようなことが書いてありました。
立ちどまって過去をふりかえることを、私はこれまでほとんどしませんでした。いつも何かにせき立てられてでもいるように、前へ前へとつっ走ってきました。自分の本を出すなど思いもよらないことでしたが、日本実業出版社の鵜野編集長のおすすめで、はからずもそんな私の半生をかえりみる機会を持てました。
猪突猛進というべきか、こわいもの知らずで立ちふさがる壁に盲滅法ぶつかってきた日々。人一倍血の気が多く、じっと我慢することができず、正義感にかりたてられてまず行動を起こし、あとから理論を組み立て戦術を練るというふうに、私は“体で学ぶ”タイプの人間です。よくもまあと、今にしてその幼稚さや無知ゆえの暴走に冷や水の出る思いもし、その結果、数多くの誤りや失敗をおかしてきていることにも気づきます。しかしいつの場合にも、よりよい状況をつくるためにひたむきであり、懸命の努力をし、その運動の中できたえられ成長してきた足あとを改めて確かめることもできました。これはむろん、私一人の闘いではありません。米よこせの風呂敷デモをした数人の主婦の集りが、戦後日本の民主的婦人運動の発祥であったことを私は今も偉大な歴史的事実として評価し誇りに思っていますが、以来二十五年、時代と深くかかわりあいながら時にははなばなしく、常に地道に、お互いの連帯で闘ってきた大勢の女の足あとが、この本です。師に恵まれ同士に恵まれ夫に恵まれ、今日の私があります。感謝せずにはいられません。
私事をいえば、二人の愛児を死なせたことが、私の終生負うべき十字架です。こどもの墓表にと貯めていた十五万円を、幼稚園再開の費用にあてた時、死者への愛を生者への愛にかえる私の姿勢が定まったといえましょう。まだまだ、なすべき仕事は山ほどあります。当面、物価の問題が私の頭の大部分を占めていますし、十八歳であとにした故郷・沖縄に保育所をつくることも夢の一つです。十字架を背負いつつ、今後も闘い続けるつもりです。
つまずきながら、頭を打ちながら歩いてきた半生を出版して公にすることに、面映ゆさを感じずにはいられません。しかし、戦後の価値観の変動をしっかりうけとめ主体的に生きる。“女の闘い”は、必ずや若い世代にひきつがれ、根強いウーマンパワーを実のらせることと信じ、この本がその一礎石となればと念じています。
昭和45年12月 比嘉正子
戦後復興と子ども達、生活者のために活動を続けた当法人創設者・比嘉正子の生きざまをもっと世に広めようと二人の女性が名乗り出てくれました。一人は様々な資料、自叙伝などから比嘉正子に陶酔した著者・井上昌子氏。もう一人は幼き頃に比嘉正子と出会い、尊敬し続けてくれていた卒園生・萩原晶子氏。
字は違えど「正子」と「昌子」。
彼女たちと語っていると時の経つのを忘れ話し尽きることがありませんでした。

そして、できあがりました。
『GHQに勝った愛』
今尚、戦禍に苦しむ子どもたちに届けよう 比嘉正子の「愛」
敗戦を乗り越えた日本、全ての統制の中で自由に買えるものがなかった時代(今のように自由に物を買うことができなかった)、人々の生命と生活を守る闘いを繰り広げてくれた比嘉正子の軌跡です。
今回は第一弾ですが、第二、第三弾と続きます。全国図書館、有名書店、Amazon、楽天ブックスで発売されております。 是非ともご購読下さいませ。
2025.9